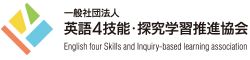高等学校学習指導要領の改訂により、2022年度から「探究」の名前の付く科目が7つ新設されます。7科目は、「古典探究」「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「理数探究」「理数探究基礎」「総合的な探究の時間」で、そのうち必履修科目になっているのが「総合的な探究の時間」です。
「総合的な探究の時間」は「総合的な学習の時間」に替わる科目です。科目名が新しくなって、学習指導要領の内容はどのように変わったのか見ていきましょう。
“高校の新しい探究学習科目「総合的な探究の時間」の学習指導要領の内容とは?” の続きを読む
学習指導要領の改訂により、高等学校の「総合的な学習の時間」は、2022年度から「総合的な探究の時間」に変更されます。「総合的な探究の時間」では、生徒が主体的に課題を設定し、情報の収集や整理・分析をしてまとめるといった能力の育成を目的としています。
「総合的な探究の時間」ではどのような授業が行われるのでしょうか。これまでの「総合的な学習の時間」の授業を参考に見ていきましょう。
“高校の探究学習科目「総合的な探究の時間」とはどのような授業なのか?” の続きを読む
文部科学省の調査によれば、探究学習の好きな児童、生徒ほど、国語や算数(数学)の平均正答率が高いという結果が出ています。探究学習とは、自分で課題を設定して情報を収集し、整理・分析してまとめ、発表するといった学習活動のことです。
生徒は「探究学習」についてどのような意識をもっているのでしょうか。「総合的な学習の時間」の授業を通じて見ていきましょう。
“中学生の「探究学習」に対する意識調査まとめ” の続きを読む
今、探究学習/アクティブラーニング/PBLなどが教育現場でも非常に注目されています。このページでは、各社が提供している様々な教材やプログラムをまとめてみました。 “中学生・高校生向け探究学習・アクティブラーニングの教材【総まとめ】” の続きを読む
「アクティブラーニング」「探究学習」「PBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング」「キャリア教育」「主体的で対話的な深い学び」といったキーワードを、ニュースや、学校などの教育現場でも、ちらほらと耳にするようになって来ました。せっかく学んだからには。その成果を競い合ったり発表し合ったりする場もあった方が良いですよね?今回は、そうした場となるような大会やコンテストをまとめてみました。
“中学生・高校生向けの探究学習・アクティブラーニングに関連した大会やコンテストの【総まとめ】” の続きを読む
高校の「学習指導要領」は2018年に改訂され、2022年から年次進行で実施されます。今回の改訂では「探究」いう言葉が中心的なキーワードと位置づけられます。
高校の新学習指導要領における「探究」の位置づけを端的に示しているのが、「 総合的な探究の時間」でしょう。「 総合的な探究の時間」は、「総合的な学習の時間」に換えて導入される科目です。
この他に、「古典探究」や「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「理数探究基礎」「理数探究」など、「探究」のついた科目が7つ新設されます。「探究」の科目ではどのような授業が行われるのか見てみましょう。
“高校の授業に新しく加わる7つの探究学習科目とは?” の続きを読む
2018年に改訂され順次移行が予定されている高校の学習指導要領では、従来の「総合的な学習の時間」に替わる形で「総合的な探究の時間」という科目が設けられています。
「探究」は地歴や数理など複数の科目にも導入されている、新学習指導要領の中心と位置づけられるキーワードです。「総合的な探究の時間」とは、具体的には何を学び育む時間なのでしょうか。
“高校の探究学習「総合的な探究の時間」の位置づけと目標” の続きを読む
2022年度から実施される高等学校学習指導要領において「探究学習」がキーワードになっています。以下の、文部科学省のページでは、「高等学校学習指導要領の改定のポイント」「要領」「新旧対照表」などをはじめ、さまざまな指針が記載されています。
“「探究学習」は2022年度から新しく導入される高等学校学習指導要領のキーワード” の続きを読む